プログラミング教室
回路図と短絡位置
マイクロビットを直接つなぐことはできないので、拡張ボードにマイクロビットを挿し、拡張ボードから出ているピンをさらにブレッドボードにつなげ、電子部品と接続しました。
ちょっと見えにくかったら申し訳ないのですが、VBUSがあって、こいつが電圧を落とす部分があります。
電源ICの入力側にVCOMBINEDが入り、MCP114が電源ICになっていて、3.3Vが出力され、それをVREGという名前にしています。
このVREGは、マイクロビットのマイコンの電源供給として使われています。
短絡させてしまったのは、電源ICで3.3Vが出た直後の部分です。
この3.3V出力がグラウンドに、このライン(赤線)で直接つながってしまいました。
この時、電源ICは3.3Vを出すのですが、グラウンドに対して電流を流してしまうため、少なくともこの電源ICは壊れるだろうと思いました。
短絡しても壊れなかった!
しかし、実際に電源ICのデータシートを見ると、この電源ICはかなり優秀でした。
3.3Vに降圧するだけでなく、サーマルシャットダウンとカレントリミットプロテクションが搭載されていました。
今回のようにショートして電流が流れた場合、電源ICの内部で発熱を検知し、一定の閾値を超えると電源ICをシャットダウンする機能が備わっていました。
さらに、カレントリミット機能により、出力電流が最大300mAに制限されていました。
そのため、壊れることがなかったのです。
これには本当に助かりました。
実際、データシートにはオシロスコープで測定した波形が掲載されていました。
上の緑の波形は、電源ICが出力している電流を示しています。
300mAほど流れ続けると、一定のタイミングで過熱(オーバーヒート)が発生し、出力電圧が元々の3.3Vから一気に0Vに落ちています。
これは、サーマルシャットダウン機能が働いたことを示しています。
動くけど安心はできない
今回、短絡保護機能のおかげで大事には至りませんでしたが、まだ安心はできません。
データシートによると、300mAが流れた後、過熱に至るまで約20msの間は電流が流れ続けていました。
短絡した部分を通じて電流は逃げたと思われますが、その後のマイコンなどにどのような影響があったかは不明です。
ピンが壊れている可能性もゼロではないので、今後の動作確認が必要です。
やらかす中で知識が身につく
やってく中で勉強することなのでしょうがないんですけど 電源の作り方は気をつけましょうね、っていうところで今回その子は 勉強になったかなと思います。
microbit自体もこういうことが きっとあると想定してるのかいい電源ICを入れてくれてて本当助かります。
初めての電子工作するにはmicrobitは結構いいかなと思います。
もし短絡させても壊れないかな?というところです。
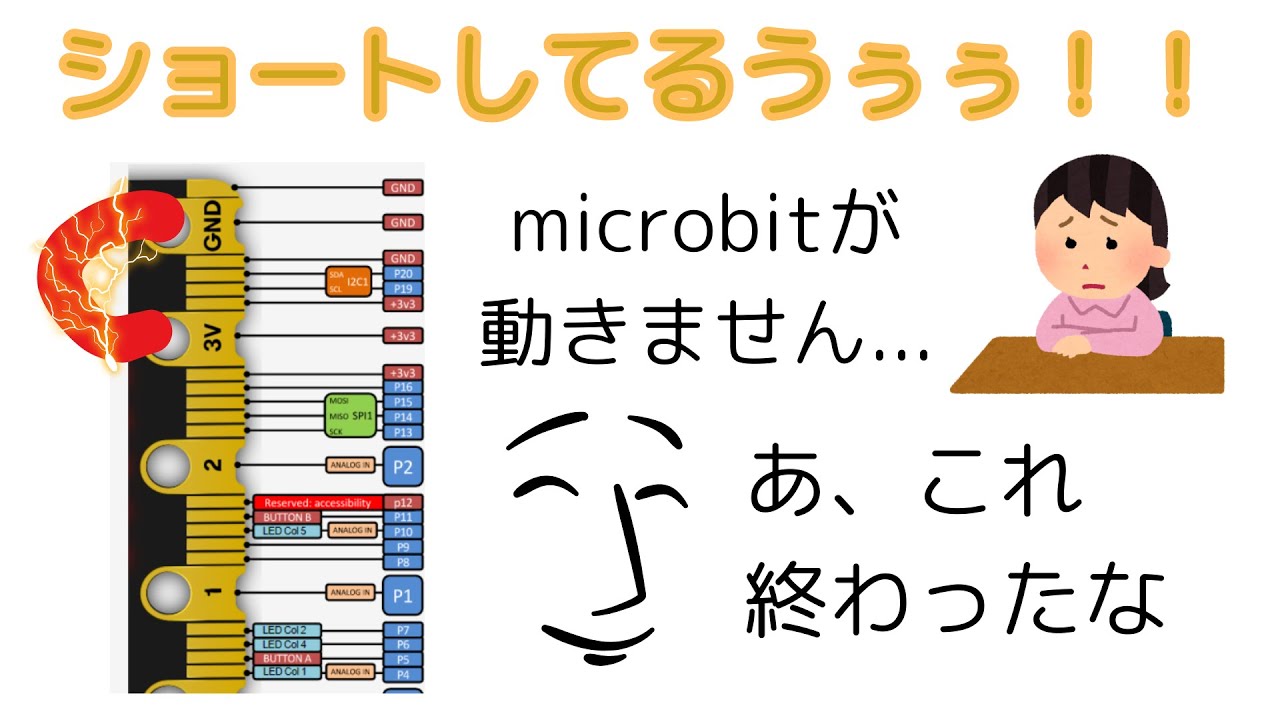

コメント